ピッタリの雨漏り修理の達人は見つかりましたか?
「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。
都道府県から職人を探す
KNOWLEDGE
Tags:屋根材

「モニエル瓦」という屋根材をご存じでしょうか?
あまり聞いたことがないという方も多いかもしれません。
モニエル瓦は一見セメント瓦に似ていますが、特殊な瓦で、塗装を行う際には注意が必要な瓦です。
こちらのページでは、「モニエル瓦」とは何か特徴やメリットデメリット、雨漏りの原因やメンテナンス方法、そしてメンテナンスを行う際の注意点についてご紹介します。
このページのコンテンツ一覧

モニエル瓦とは、瓦と名前についてはいますが、日本の伝統的な瓦とは別物です。
以前にご紹介した「セメント瓦」に近い瓦で、セメント瓦がセメントを主成分にした瓦であるのに対して、モニエル瓦はコンクリートを主成分にした瓦です。コンクリートはセメントに砂や砂利を混ぜ、瓦の形に押し出して成型し、着色のためスラリー塗装とクリア塗装を行います。
スラリー塗装は約2mm~3mmのスラリー層という防水層を形成します。
この製造過程において、当時耐久性を高めるためによく使用されたアスベストや、粘土瓦のように窯で焼くなどの工程が不要であり二酸化炭素の発生も極力抑えられています。そのため環境にやさしい屋根材ともいえます。
また製造コストが瓦よりもかからないため価格が抑えられたことも普及した一因でした。
セメント瓦と成分が近いため、モニエル瓦もセメント瓦の一種として扱われることもあります。
モニエル瓦は昭和48年(1973年)に技術導入され、オーストラリアのモニエル社と日本のクボタが共同開発を行い、日本モニエル株式会社が販売していました。その後高度経済成長期にかけて、セメント瓦と同じように、当時は高価だった粘土瓦が高い住宅需要に追いつかず、代わりに安価に手に入る瓦として普及しました。
数多く販売され人気があったことから、「コンクリート瓦」ではなく、販売会社である「モニエル」の名前をとって「モニエル瓦」と通称されるようになりました。
「乾式コンクリート瓦」や「乾式洋瓦」と呼ばれることもあります。
2010年に日本モニエル株式会社が廃業し、現在では生産されていません。
セメント瓦について詳しくは「セメント瓦の雨漏り原因とメンテナンスについて」をご覧ください。
モニエル瓦は着色過程が独特で、スラリー塗装を行ったあとクリア塗装を施し、スラリー層という防水層が約2mm~3mmの厚みがあります。
このため強い雨や風にも耐える高い防水性を持っています。
モニエル瓦は素材がコンクリートであり、素材そのものが丈夫です。モニエル瓦の耐用年数は約20~30年。
屋根材自体に厚みがあるため熱や音を通しにくく、遮熱性や防音性にも優れています。
高度経済成長に広く普及した化粧スレートには、強度を高めるためにアスベストが含有されていることが多く、社会問題にもなりました。しかし上述したようにモニエル瓦には含まれておらず、製造過程で二酸化炭素もほとんど排出しないため環境にやさしい屋根材です。
スラリー塗装により豊富なカラーバリエーションと、もともと輸入屋根材のため洋風なデザインが楽しめます。
形状も幅広く、粘土瓦を模した和型、洋風で立体的なフォルムの洋型、フラットで和風も洋風もどちらにも合う平型、S字のデザインが特徴的な南欧風のS型など豊富なデザインがあり、住宅に合わせて選ぶ事が可能です。
モニエル瓦和型

モニエル瓦平型

モニエル瓦S型

モニエル瓦は素材がコンクリートのため、やや重い屋根材です。
金属屋根の重さは1㎡あたり5kgにたいして、モニエル瓦は1㎡あたり約43kgと約8倍の重さがあります。
屋根材が重いとその分建物にかかる負荷が大きくなることに加えて、地震の際の揺れも大きくなってしまいます。
モニエル瓦はコンクリートが主材料のため、屋根材そのものには防水性能がありません。
スラリー塗装が形成するスラリー層は強固な防水層となりますが、このスラリー層は経年劣化で少しずつ劣化し、施工後15年程度でなくなってしまいます。
そのため10~15年に一度塗装によるメンテナンスが必要となりますが、スラリー層のある屋根材には注意が必要です。
スラリー層には塗装をはじく性質があるため、再塗装の際には、この元々あるスラリー層をきれいに除去する必要があります。
高圧洗浄でとれない分は、手作業で取り除いていきます。
除去せずに上から塗装してしまうとせっかく塗装した新しい塗装は数年たたずに脆くなったスラリー層と一緒に剥がれてしまい、こうしたトラブルが多く発生しています。
スラリー層を除去する際には汚れた水が大量に発生するため、この水が飛散しないよう考慮しないとご近所トラブルになる可能性もあります。
以前はスラリー層のある屋根材への塗り替えは困難とされていましたが、現在ではスラリー層がある屋根への塗り替え専用の下塗り材が開発されています。モニエル瓦を再塗装する際には、この専用の下塗り材を使用する必要があります。
これも誤ったシーラーを塗装すると剥落など早期劣化や施工不良の原因になってしまいます。
専用塗料には下記のようなものがあります。
・スラリー洋瓦用シーラー(水谷ペイント株式会社)
・ヤネフレッシュSi(エスケー化研株式会社)
・モニエルパワープライマー(株式会社アステックペイント)
表面を保護するスラリー層は徐々に紫外線によって劣化し、色が薄くなって色褪せが起こります。またツヤが落ちると退色します。
この状態からすぐに雨漏りが発生することはありませんが、塗料が劣化しているサインのため防水機能が低下しているということでもあります。
劣化が進行する前に再塗装で機能を回復することを検討してください。
塗料が劣化して防水機能が低下すると、雨水が屋根材に溜まりやすくなり、苔やカビが発生することがあります。
特に北側の屋根や日当たりの悪い場所では発生しやすくなります。
苔やカビが生えると常にそこに水がたまった状態となり、屋根材の劣化は進行します。屋根材から内部の防水紙や野地板まで到達すると腐食や雨漏りリスクが高まります。
劣化が進んだり地震などでクラックが生じ隙間から雨水が侵入した場合や施工中に水が混入した場合、下塗り・下地調整が不十分であった場合には塗膜の膨れが発生します。また蓄熱による熱収縮も塗膜の膨れを引き起こします。
塗膜が膨れている場合は、塗料の機能が失われいるサインなので、早めの塗り替えをお薦めします。
塗り替えてすぐに塗膜が剥がれてくる場合は、旧スラリー層が十分に除去できていなかった、適切な下塗り材が使用されていなかったなど施工不良が疑われます。
塗膜が剥がれてしまうと素地がむき出しとなってしまい、美観を損ねるだけではなく、成分のカルシウムが流出してしまい、表面にざらつきや凹凸が生じて雨が溜まりやすく、屋根の劣化がさらに進行してしまいます。
こうなると塗装した際の見栄えも悪くなってしまいます。
地震や強風など強い衝撃で瓦がズレたり、破損することがあります。
こうしてできた隙間からは雨水が侵入して雨漏りを起こしやすくなります。
モニエル瓦で雨漏りが発生する原因は、瓦のズレや割れなどの破損や、屋根材そのものの劣化の他に、板金部材や漆喰の劣化などが考えられます。
自然災害や劣化によって発生した隙間から雨水が内部へと侵入し、屋根材の下にある防水紙へと到達します。この防水紙が最終的に雨漏りから守っているのですが防水紙の寿命はモニエル瓦よりも早いことが多く、防水紙の寿命が切れている場合にはその下の野地板にまで侵入し、腐食させてしまいます。
また大量の雨水が侵入すると防水紙の劣化も早めてしまい、雨漏りのリスクを高めます。
屋根材の他にも、屋根に降った雨水を流す樋の役目をしている谷板金は劣化しやすく雨漏りの原因になりやすい箇所です。
経年劣化によって変形が発生すると、正常に雨水を排水できず水が一か所にとどまり、板金に錆や穴を発生させてそこから雨漏りが起こります。
モニエル瓦はコンクリートの表面を覆うスラリー層が劣化でなくなってしまう前に定期的に塗装を行う必要がありますが、もしもそれを怠ってしまうと屋根の防水機能が切れて、雨水を吸収し、水分を含んだ状態になります。カルシウムが流出することで表面に凹凸が発生するので苔やカビも発生しやすく、水分が留まることで屋根材の劣化を推進してしまいます。
滞留した雨水がやがて防水紙や野地板にまで影響を与えて雨漏りが発生します。
屋根のてっぺんを固定し雨水の侵入を防ぐために、漆喰が使用されています。この漆喰が経年劣化すると剥がれたりすることで隙間から雨水が侵入して雨漏りを起こすことがあります。
色褪せや退色が発生しており、瓦そのものが大きなダメージを受けていない場合には、再塗装を行います。
モニエル瓦は塗装によるメンテナンスを10~15年単位で行うことで耐久性を保つことができます。
瓦のずれ、欠け、割れなど軽微な場合には、コーキングやパテで補修を行います。
瓦が大きく破損している場合には、モニエル瓦は生産中止となっており、新しい製品を入手するのが困難なため、葺き替えを検討することになります。
谷板金の劣化の場合には谷板金の補修や交換、漆喰の劣化は漆喰の詰め直し工事を行います。
屋根材全体が劣化しているような場合には、モニエル瓦は生産が終了しているため、葺き替え工事をすることになります。
金属屋根など軽い屋根に葺き替えすることで耐震性も向上し屋根材だけでなく野地板の補修や防水紙も新しいものにするため屋根全体の機能が回復し耐久性が大きく向上します。
既存の屋根の上に新しい屋根を被せるカバー工法には既存の屋根を解体しない分コストが抑えられ、工期も短くなるメリットがあります。しかしカバー工法は平らでない屋根には施工が困難で、さらに重いモニエル瓦に新しい屋根をかぶせると屋根が重くなり耐震性が下がってしまいます。
そのためモニエル瓦にカバー工法を行うことはおすすめできません。
\モニエル瓦からの屋根修理や塗装、雨漏り修理はお近くの雨漏り修理の達人にお任せください!/
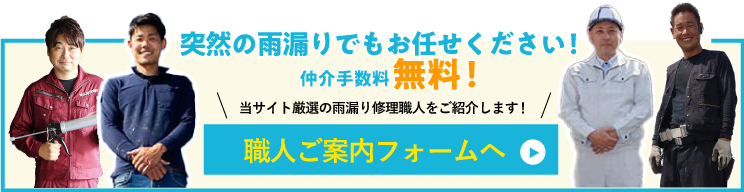
コンクリートを主材料とするモニエル瓦は環境にも優しい屋根材として人気がありましたが、今はもう生産中止しています。
モニエル瓦で雨漏りを起こさないためには、10~15年単位で塗装を行うことが重要ですが、塗装の際にはスラリー層の確実な除去や、専用の下塗り材を使用するなど注意点があります。
もしもこれらを行わないとせっかく塗装を行っても数年で剥がれてしまいます。
塗装を依頼するには、経験と知識が豊富な職人に依頼するようにしましょう。
塗装でメンテナンスできないほど劣化している場合には葺き替え工事をすることで屋根の機能が回復し、建物自体の耐久性を延ばすことにもつながります。
●雨漏り修理の達人によるモニエル瓦の施工実績は下記をご覧ください。
千葉市花見川区にて瓦葺き直し・棟積み直し
京都市右京区にて雨漏り修理
「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。
 雨漏りでよく検索されている
雨漏りでよく検索されている よく読まれている記事
よく読まれている記事お気軽にご質問ください
LINEでかんたん
問い合わせ&職人案内