ピッタリの雨漏り修理の達人は見つかりましたか?
「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。
屋根修理にかかる費用は確定申告で2つの控除対象!さらに他にも減税措置が
都道府県から職人を探す
KNOWLEDGE
Tags:雨漏り修理の費用

「屋根の修理にかかる費用は、確定申告で2つの控除対象になります」と言われても、それぞれの控除内容や違い、さらに申請方法がわからないという人も少なくないはずです。毎年申請するのが面倒な確定申告ですが、どうせ申請するなら損はしたくないものですよね。
そこで今回は、災害における屋根修理で確定申告の控除対象になるものの特徴や控除額の算出例、さらにその他の減免措置などについても解説します。本記事を読めば、屋根を修理した時に確定申告で損することはなくなります。
このページのコンテンツ一覧
災害で屋根に損害を被った際、修理にかかる費用は確定申告で控除の対象になります。さらに屋根の修理費用は、確定申告において控除の対象が1つだけではありません。
災害で屋根に損害を被った際、修理にかかる費用は確定申告において以下2つの控除対象になります。
ここでは、これらの控除方法についてくわしく解説していきます。
「雑損控除」とは、災害により資産(住宅や家財など)が損害を被った場合に、利用できる控除方法のことをいいます。
たとえば、台風などの自然災害で飛来物により屋根が破損した場合、その修理にかかった費用が控除の対象となります。確定申告においては所得控除に分類され、計算式で算出された金額を「所得」から控除できます。
また「雑損控除」には、最長3年間の繰越期間が設けられています。
一方「災害減免法による所得税の軽減免除」とは、災害で住宅や家財が損害を被った時に、その損害額や所得など一定の条件を満たした場合に利用できる控除方法のことをいいます。
「災害減免法による所得税の軽減免除」では、確定申告を申告した人の年間所得金額に応じて、所得税(復興特別所得税も含む)が免除または減額されます。
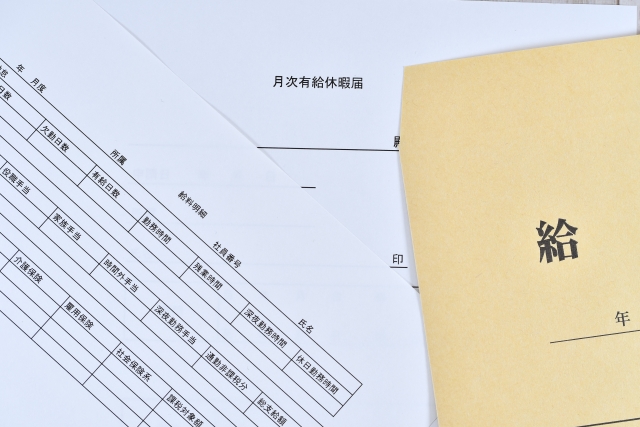
「雑損控除」および「災害減免法による所得税の軽減免除」における控除対象の適用には、以下3つの条件をクリアする必要があります。
これら3つの条件について「雑損控除」「災害減免法による所得税の軽減免除」双方の違いを確認していきましょう。
控除対象の適用条件、1つ目は「資産の範囲」です。
資産の範囲については、それぞれ以下の適用条件が設けられています。
| 雑損控除 | 住宅・家財 |
| 災害減免法による所得税の軽減免除 | 住宅・家財(保険金等の補填額を差し引いた損失額が時価の1/2以上ある場合のみ適用) |
「雑損控除」における資産の範囲が「住宅・家財」であるのに対し「災害減免法による所得税の軽減免除」における資産の範囲は「住宅・家財の一部」と限定されているため、損失額が1/2未満となる場合には雑損控除を選択すべきでしょう。
控除対象の適用条件、2つ目は「損害の原因」です。
損害の原因については、それぞれ以下の適用条件が設けられています。
このように、「雑損控除」は「災害減免法による所得税の軽減免除」では適用外となる「盗難」「横領」といった損害の原因までカバーしています。
なお雑損控除における「横領」では、「詐欺」や「恐喝」は対象外となります。
控除対象となるための適用条件、3つ目は「納税者の所得制限」です。
納税者の所得制限については、それぞれ以下の適用条件が設けられています。
| 雑損控除 | 制限なし |
| 災害減免法による所得税の軽減免除 | 1,000万円以下(災害を被った年における所得額の合計) |
損害を被った年における納税者の所得額が合計1,000万円を超える場合には、適用となる所得に制限がない「雑損控除」を利用しましょう。

「雑損控除」および「災害減免法による所得税の軽減免除」の控除額を計算する際には、両者とも「差引損失額」を基準にします。
「差引損失額」は、以下のように計算されます。
〈差引損失額 = 損害金額 + 災害関連の支出額 ー 保険金などで補填される金額〉
なお屋根修理にかかる費用は、ここでいう「災害関連の支出額」に該当します。
ここでは、差引損失額を基準とした両者における控除額の計算方法を見ていきましょう。
「雑損控除」における控除額の計算方法は、以下の2通りがあります。
これら2つのうち、金額が大きい方を控除額として適用します。
「災害減免法による所得税の軽減免除」における控除額の計算方法は、所得金額に応じて以下のようになります。
| 所得金額 | 災害減免法による所得税の軽減免除額 |
| 500万円以下 | 全額 |
| 500万円超〜750万円以下 | 1/2 |
| 750万円超〜1,000万円以下 | 1/4 |
「雑損控除」と異なり、「災害減免法による所得税の軽減免除」では控除対象となる所得金額が限定されているため注意が必要です。

ここでは、災害により屋根が損害を被り修理をした例に基づいて「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」の控除額を算出していきます。
ここでは、以下の例に沿ってそれぞれの控除額を算出していきます。
【例】控除額における算出の条件
| 所得金額の合計(年間) | 600万円 |
| 差引損失額 | 100万円 |
| 災害関連の支出額 | 50万円 |
なお、これらの全額を「雑損控除」「災害減免法による所得税の軽減免除」における対象の資産とするとともに、基礎控除を除き「雑損控除」以外の控除はなかったものとします。
それでは、それぞれの控除額を見ていきましょう。
「雑損控除額」と「所得税額」をそれぞれ計算していきます。
以下2つの方法で、雑損控除額を計算していきます。
【計算方法1】
100万円(差引損失額) ー 600万円(所得金額) × 1/10 = 40万円
【計算方法2】
50万円(差引損失額に含まれる災害関連の支出額)ー 5万円 = 45万円
いずれか金額の多い方が控除額として適用されるため、雑損控除額は以下のとおりです。
雑損控除額:450,000円
所得税額の計算にあたって、まずは課税所得を求めていきます。
【課税所得】
600万円(所得)ー 48万円(基礎控除)ー 45万円(雑損控除)= 507万円(課税所得)
次に、計算した課税所得を用いて所得税額を計算します。
【所得税額】
507万円(課税所得)× 20万円(所得税率)ー 427,500円(控除額)= 586,500円(所得税額)
以上の計算から「雑損控除額」と「所得税額」は、以下のようになります。
雑損控除額:450,000円
所得税額:586,500円
「災害減免法による所得税の軽減免除」における控除額の計算では、はじめに所得税額から求めていきましょう。
前回同様、課税所得から計算します。
【課税所得】
600万円(所得)ー 48万円(基礎控除)= 552万円
次に、課税所得を用いて所得税額を計算します。
【所得税額】
552万円(課税所得)× 20万円(所得税率)ー 427,500円(控除額)= 586,500円
ここで「災害減免法による所得税の軽減免除額」を確認します。今回の例では、所得金額の合計が600万であるため「災害減免法による所得税の軽減免除額」は所得税額の1/2となります。
以上のことから「災害減免法による所得税の軽減免除額」と「所得税額」は、以下のようになります。
災害減免法による所得税の軽減免除額:293,250円(586,500円 × 1/2 = 293,250円)
所得税額:293,250円
なお今回の例では、2022年4月1日時点における法令等をもとに上記の計算をしています。あくまで一例として捉えるようにしましょう。

屋根修理の確定申告には、どのような書類が必要なのでしょうか。ここでは、両者における確定申告に必要な書類を解説していきます。
それでは、順に見ていきましょう。
確定申告で「雑損控除」を受ける際に必要な書類は、以下のとおりです。
一方、確定申告で「災害減免法による所得税の軽減免除」を受ける際に必要な書類は、以下のとおりです。
このようにいずれも申請に必要な書類が多く、すべての書類を準備するには時間を要するため、申請の際には早い段階から必要書類を準備するようにしましょう。
これまで見てきた所得税控除のほかにも、災害による損失の程度次第では以下に代表されるような所得税以外の減免措置も受けられます。
ひとつずつくわしく解説していきます。
個人住民税では、所得税同様に「雑損控除」が対象になるだけでなく、条例の減免措置なども受けられます。
所得税では「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」のいずれか一つのみを適用できましたが、一方の個人住民税では「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」の両方を適用できるといったメリットがあります。
なお、各自治体によって減免措置の運用や対象者は異なるため注意が必要です。
災害により住宅や家財などの財産が概ね1/2以上の損害を被った場合には、申請することにより国民年金における保険料を免除できます。
通常、台風などの自然災害で屋根が損害を被った場合には、被害の範囲が財産の1/2に満たないことが多いため、国民年金は適用されないケースが多く見られています。
災害により住宅や家財における価格の3/10以上に損害を被った場合には、国民健康保険税の減免措置が受けられます。
なお、この減免措置の基準については、各自治体によっても異なるため申請の際には事前に確認するようにしましょう。

今回は、災害など屋根を修理する際に確定申告の控除対象になるものの特徴や控除額の算出例、その他の減免措置などについて解説しました。
災害などで損害を被った屋根の修理にかかる費用は、確定申告で「雑損控除」「災害減免法による所得税の軽減免除」といった2つの控除対象になります。さらに「個人住民税」に代表されるその他の減免措置も適用になる可能性もあるため、税金に対する正しい知識と持った控除の選択が必要になります。
屋根修理における確定申告では「災害の修理にかかった費用を証明できる領収書」が必要になるため、万が一の災害に備えて、早い段階から信頼できる専門業者を見つけておきましょう。
雨漏り修理をはじめとする屋根修理の専門業者を検索できる「雨漏り修理の達人」では、災害における屋根修理の経験豊富な優良業者が多く掲載されているので、安心して屋根の修理をおまかせできます。
屋根修理の業者探しなら、ぜひ一度「雨漏り修理の達人」を活用してみてくださいね。
雨漏りを確実に修理する厳選された職人だけを掲載。
仲介手数料なし。直接連絡OK!
Step1

お住まいの都道府県をクリック
Step2

各職人のプロフィールや実績、強みを比較検討
Step3

そのまま直接職人と話せます
Point1
急を要する雨漏り。サイトを通さず迅速に直接職人とやりとりが可能です。
Point2
紹介料などの手数料は一切かかりません。無料でご利用いただけます。
Point3
雨漏り修理の実績豊富な専門業者のみを掲載しています。
弊社では掲載業者様から月数千円の会費をいただいております。
他社の業者紹介サイトのように、月数万円や年数十万の会費に加えて案件紹介1件につき数万円や成約につき受注金額の2割〜5割の仲介手数料などは一切いただいておりません。
そのため、お客様にもご負担なくご利用いただけます。
どれだけ熟練の雨漏り修理職人であっても、葺き替えやカバー工法が必要なケースでは、コーキングだけで雨漏りを完全に止めることはできません。
「雨漏り修理の達人」に登録している職人たちは、まず丁寧な点検・診断を行い、雨漏りをきちんと止めるために本当に必要な修理内容と、その場合の適正価格をお伝えします。
また、直らないとわかっていながら「2〜3万円で直ります」といった不誠実な提案をするようなことは一切ありません。
そのうえで、最終的な工事内容やご予算のご判断は、もちろんお客様のご意思を最優先にしています。無理におすすめするようなことは一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談だけでも歓迎ですので、「まずは話を聞いてみたい」という方もお気軽にご利用ください。
「このくらいの小さな雨染みなら大したことないから大丈夫かな」と思われるお気持ちはわかりますが、初期の段階こそ対処されることをおすすめします。
なぜなら雨漏りの場合、放置しても自然に直ることがないからです。
雨漏りして室内に症状がでている時にはすでに家の内部に雨が侵入しており、放置してしまうと雨のたびに水が入り込んで、住宅の内部で広がってしまい、放置すればするほど修理の費用が高くなってしまいます。
最初は瓦のズレ直しや漆喰補修など部分的な補修で済んでいたものが、放置してしまうことで、葺き替えなど大がかりな工事が必要になるリスクが高まります。
まずはどんな状態なのか、相談されて状態を把握されることをおすすめします。
はい、ご相談だけでも大歓迎です。
「雨漏りかどうかわからない」「修理するかどうか決めていない」「まずは被害の状態や費用の概算を知りたい」といったご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
雨漏り修理で最も重要なのは正確な原因の特定です。
雨漏りは屋根だけでなく、外壁や板金、コーキング、ベランダ、笠木など様々な小さな隙間や劣化から発生します。天井からの雨漏りなので屋根からだと思ったら違う場所だったということは珍しくありません。また原因が一か所だけとは限らず複数のこともあります。
DIYで一時的に対処できる場合もありますが、自分で行った場合、雨漏りの原因を見落としたままになることも多く、あとで余計な工事や出費につながるリスクがあります。また水の流れを理解した上で正しい施工を行わないと余計に悪化してしまうケースもあります。
長期的に安心して住まいたい方には、原因の正確な特定と原因に合った工事を正しく行える業者の依頼を推奨いたします。
ご予算に不安があるなかでの雨漏り修理、とても悩ましいことと思います。
当サイトにご相談いただく方の中にも、「なるべく費用を抑えたい」というご要望は少なくありません。
とはいえ雨漏りを放置してしまうと、建物内部の腐食やカビの発生など、修理費用が大きくふくらむ可能性があるため、早めの対応が結果的にコストを抑えることにつながる場合もあります。
状態や職人によっては、応急処置での一時的な対処や原因箇所を絞った部分修理、必要な工事を段階的に行うご提案、必要なところだけお金をかけるご提案など、お客様のご事情やご予算に合わせてできるだけ負担を少なく済ませるための選択肢をご提案いたします。
ご相談や見積りは無料で、予算に応じた柔軟なご提案ができる職人をご紹介しますので、まずは状況をお聞かせください。
「修理が必要かどうか分からない」といった段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
雨漏り修理は商品ではなく、それぞれのお家によって原因も築年数などの状態も異なるため、一律で価格をだすのは難しい工事です。
雨漏りの原因が一か所のひび割れだけであり、進行も少ないような場合には3万円のコーキング工事で直る事例ももちろんあります。
しかし屋根や外壁などの劣化が進んでいたり、複数箇所から雨漏りしているような場合は、根本的な工事(葺き替え・カバー工法など)が必要になることもあります。そのような場合にはコーキング工事など3万円の工事だけでは直しきれず、また雨漏りが発生してしまうのです。
実際に「2〜3万円で直ると言われてコーキングだけ打ってもらったが、結局直らなかった」というご相談が当サイトにも寄せられています。
雨漏りが発生しているということは、経年劣化によって屋根などの外装が修繕の時期を迎えているサインである場合が多いです。コーキングだけで済ませてしまうと、一時的には止まっても、別の場所から再発したり、内部劣化が進んでしまうことも少なくありません。
重要なのは雨漏りの原因や状態をしっかり見極めた上で、今のお家の状態を知り、そしてどんな工事が必要なのかを知ることです。
当サイトでは、調査を行って状況をご説明した上で、お客様から費用面や希望をうかがいながら、お客様やお家に合わせた「最適な工事」をご提案できる職人をご紹介しています。
無理に高額な工事をすすめることはなく、お客様の状況に合わせた最適な提案を行いますので、まずはお気軽にご相談ください。
雨漏り修理は、雨漏りの原因や進行の度合いよって必要な工事が大きく異なります。大体の目安は以下になります。
コーキング補修(窓・外壁):一か所あたり5〜10万円
バルコニー防水補修:10〜50万円
天井・屋根下地交換:5〜50万円
屋根全面葺き替えを伴う場合:数十万円〜100万円以上
シロアリ補修・躯体補修:10〜100万円以上
まずは被害の状態を調査することが重要です。見積りをご依頼ください。
雨漏りがなかなか直らない大きな原因は、雨漏りの特定が行えていないことや、残念ながら依頼された業者の施工不備などが考えられます。
雨漏り修理においては、雨漏り箇所を正確に突き止めることが最も重要なポイントとなります。雨漏り箇所を正確に突き止めないまま場当たり的に工事を行っていたり、雨漏りに対して適切な施工が行えていないと雨漏りは再発してしまいます。
雨漏りが止まらないとストレスも大きく、何度も工事を依頼すると工事費用もかさんでしまいます。雨漏り修理の業者を選ばれる際には、雨漏りの経験が豊富であり、アフターフォローもしっかりしている業者に依頼すると安心です。
雨漏り修理の達人では雨漏り修理の経験が豊富な厳選された業者をご紹介しています。
「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。
 雨漏りでよく検索されている
雨漏りでよく検索されている よく読まれている記事
よく読まれている記事
お気軽にご質問ください
LINEでかんたん
問い合わせ&職人案内