ピッタリの雨漏り修理の達人は見つかりましたか?
「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。
都道府県から職人を探す
KNOWLEDGE
「雨漏りが発生したけど、業者に頼むと高そう…」「ホームセンターに防水テープが売っていたから自分でやってみよう」こうした理由から、DIYで雨漏り修理を試みる方は少なくありません。
しかし実際には、DIYによる修理で状況が悪化してしまったケースも多く報告されています。
この記事では、DIY修理のよくある失敗例から、正しい対処法、専門業者に頼むべきタイミングまで詳しく解説します。
このページのコンテンツ一覧

雨漏りが発生したとき、「とりあえず応急処置をしてみよう」と自分で対処しようとする方は少なくありません。しかし、雨漏り修理は一見簡単そうに見えて、実は専門的な知識と技術が必要な分野です。自己判断で対応しようとすると、かえって状況を悪化させてしまうことが多くあります。
ここでは、DIYによる雨漏り修理が失敗しやすい理由について、詳しく解説します。
雨漏りの原因は、「屋根のヒビ」や「壁のヒビ」など目に見える部分だけではありません。実際には、以下のように見た目では気づきにくい“複合的な要因”が絡んでいるケースが多く存在します。
また、水の性質上、屋根から伝って壁や天井に回り込み、実際の侵入箇所と雨漏りの症状が出る箇所がズレることはよくあることです。たとえば、屋根の棟板金の隙間から入った水が梁や天井を伝い、離れた部屋の天井にシミとして現れることもあります。
そのため、「ここから漏れているはず」と思って応急処置をしても、本当の原因を見逃してしまえば何の意味もなく、むしろ状況が悪化する危険性すらあるのです。
DIY修理で最も多いのが、防水テープやコーキング材を使った応急処置です。しかし、これらの応急材を適切に使わないと、逆に雨漏りが悪化するケースがあります。
たとえば、防水テープを隙間にベタっと貼ってしまうと、一時的には水の侵入が止まったように見えるかもしれません。しかし、内部で水が逃げ場を失い、柱や下地材、断熱材に溜まることで、
といった目に見えない深刻な被害を引き起こす可能性があります。
特に危険なのは、防水層や通気層の存在を理解せずに施工してしまうことです。
こうした誤った処置をしてしまうと、本来雨水を外に排出するはずの構造が機能不全になり、内部に水が溜まってしまう状態になります。
さらに、防水処置のつもりで厚く塗ったコーキングが、逆に水をせき止めてしまい、内部に滞留する「水たまり」を作ってしまうケースもあります。
もうひとつ忘れてはならないのが、安全面でのリスクです。DIYでの雨漏り修理は、屋根やベランダ、天井裏など高所や足場の悪い場所での作業になることが多く、慣れていない人が作業を行うと落下事故やケガの危険があります。
また、天井裏などには照明や配線が通っているため、誤って電気設備に触れて感電する恐れもあります。知識のないまま無理に手を出すことは、非常に危険です。
雨漏りの修理には、条件次第で火災保険が使えるケースがあります。しかし、自己流の修理によって状況を悪化させた場合、
といった理由から、保険の適用対象外になる可能性もあります。
特に、台風などの風災被害のあとにDIYでの補修を行ってしまい、後から本格的な修理を依頼しようとしても、「自己修理によって証拠が破損していた」という理由で申請が却下される例も少なくありません。

「とりあえず応急処置をしたい」「自分で直せば費用もかからない」
そんな思いからDIYで雨漏り補修に取り組む方は少なくありません。しかし、雨漏り修理は建物の構造や水の動きを深く理解したうえで行わなければ、逆に症状を悪化させてしまう危険性があります。
ここでは、実際にあったDIY修理の失敗例をご紹介します。いずれも一見すると簡単な補修のように思えますが、結果として被害が広がり、専門業者による大掛かりな修繕が必要となったケースです。
ある住宅の施主が、「天井からポタポタと水が垂れてきた」とのことで、屋根の板金や瓦のつなぎ目をコーキングで埋めたという事例です。一見、目視で隙間があるように見えた箇所に、ホームセンターで購入したコーキング材をたっぷり充填。作業後数日は漏水が止まったように見えたため、「自分で直せた」と安心してしまったそうです。
しかし、実際は雨水の通り道(排水経路)をふさいでしまったことで、屋根材の下にたまった水が逃げ場を失い、徐々に下地材へと侵入。最終的には野地板や垂木(屋根の骨組み)まで腐食し、屋根全体の修繕が必要になりました。
このケースの失敗の原因は、「見える隙間が雨水の侵入口とは限らない」という点を理解していなかったこと。雨仕舞(あまじまい)と呼ばれる雨水の流し方には構造的な知識が必要で、ただ隙間を埋めればよいわけではないのです。
こちらは、台風のあとにスレート屋根材がズレているのを見つけた住人が、「危ないから」と応急処置としてガムテープで固定したという例です。
最初は「これで当面は大丈夫」と思っていたところ、数日後の強風でテープが剥がれ、ズレていた屋根材が完全に飛散。そこから大量の雨水が侵入し、天井裏からの漏水に発展。結果的に、天井のボードが落ち、室内のクロスや家具にも大きな被害が出てしまいました。
テープ固定の問題点は、耐候性・防水性・強度のいずれも屋根材固定には不適切であること。また、屋根材がズレる=下地にも損傷がある可能性が高いため、根本的な原因を見極めずに応急処置だけを施すと、かえってリスクが増します。
ベランダの床面にひび割れが見つかり、「雨が入るのでは」と心配になった施主が、DIY用の防水塗料をホームセンターで購入し、上から塗って補修したというケースです。
しかしこの施工は、既存の防水層の素材と塗料の相性が悪かったため、数ヶ月も経たないうちに塗膜がボロボロと剥離。しかもその下では、既に防水シートの劣化が進行し、水分が建物内部に入り込んでいました。
この事例で問題だったのは、「ベランダの防水工事には下地処理やプライマー処理が必要であり、塗料選びも既存素材との相性を考慮しなければならない」という基本を知らず、見よう見まねで作業してしまった点です。
結果として、床下の合板が腐食し、支持力を失ってベランダ全体の防水改修が必要に。DIYで済ませようとした数千円の作業が、数十万円の大規模工事に発展してしまいました。

雨漏りを見つけたとき、「業者に頼む前に、自分でできることはないか?」と考える方も少なくありません。確かに、応急処置で被害の拡大を防ぐことは重要です。しかし、DIYによる雨漏り修理には大きな限界とリスクがあることも理解しておきましょう。
DIYで対応できる範囲は、あくまで一時的な応急処置にとどまります。以下のような対応が主な内容です。
こうした対応は、被害の拡大を抑えるには非常に有効です。特に、業者の手配に時間がかかる場合や、台風・大雨など緊急時には役立つ手段です。
しかしながら、「ブルーシートで覆っておけば安心」「コーキング材で隙間を埋めれば直る」といった考えで本格的な修理を自己判断で行うのは非常に危険です。
防水層の構造を壊してしまったり、水の逃げ道を塞いでしまったりすると、雨漏りの範囲が見えないところで拡大し、住宅全体の寿命を縮める結果になりかねません。
特に築年数の経った住宅では、構造体そのものが傷んでいるケースも多く、表面的な修理では根本解決にならないことがほとんどです。
DIYで最も注意すべきなのが、「屋根に上って作業をしよう」とする行為です。
こうしたリスクを避けるため、プロの職人は足場を設置し、安全帯(命綱)を装着し、専用の靴や工具を使って作業を行います。一方で、素人が無装備で屋根に上ることは非常に危険で、実際に毎年多数の転落事故が報告されています。
また、屋根上にはテレビアンテナや配線など、感電のリスクがある箇所も存在します。こうした危険性を考えれば、安全のためにも「屋根に上ること自体をしない」ことが最善の選択です。

「自己流でコーキングしてみたけど、結局また雨漏りが…」という声は決して珍しくありません。DIYで状況が改善しなかった場合、あるいは悪化してしまった場合には、できるだけ早く専門業者に相談することが重要です。
放置や遅れは、雨漏り被害をどんどん深刻化させていきます。以下のような二次被害のリスクが高まります。
特に木造住宅では、水分が原因で躯体の耐久性が著しく損なわれることがあるため、「この程度なら大丈夫」と自己判断せず、できるだけ早期にプロの目で診断してもらうことが、被害を最小限にとどめるコツです。
プロの雨漏り修理業者であれば、目視だけでなく、散水試験やサーモグラフィ、ドローンによる屋根点検など、科学的なアプローチで原因を特定してくれます。見えない部分にこそリスクが潜んでいる雨漏り修理では、こうした技術力が大きな違いを生みます。
業者に現地調査を依頼する際には、「これまでに行ったDIY修理の内容」を包み隠さず伝えることが非常に重要です。
といった情報があると、業者側も正確に原因を分析し、的確な修理提案がしやすくなります。
逆に情報が曖昧なままだと、調査や修理が二度手間になったり、不要な範囲まで工事が必要になる場合もあります。大切なのは、早期に信頼できる業者に相談し、プロの判断に委ねることです。
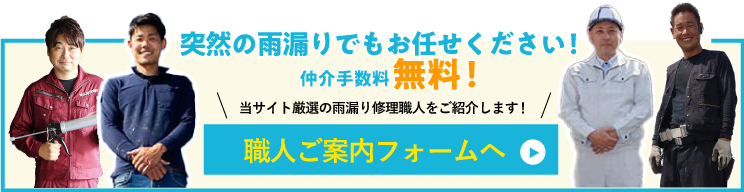

DIY修理で雨漏りが悪化してしまった場合、迅速かつ的確な対処が必要です。しかし、いざ業者を探そうと思っても、「どの業者に頼めば本当に安心なのか」と迷う方は多いでしょう。そこで、信頼できる業者を選ぶ際に確認しておきたいポイントを詳しく解説します。
雨漏りの修理では、「どこから水が入ってきているのか」を正確に突き止めることが最も重要です。見た目だけでは判断できないケースも多いため、次のような詳細な調査ができるかどうかを確認しましょう。
これらを実施してくれる業者であれば、原因の見落としによる再発リスクを大幅に減らすことができます。見えない部分まで丁寧に診断してくれるかどうかが、信頼できるかどうかの第一歩です。
雨漏り修理と一口にいっても、必要な工事の内容や規模はケースによって異なります。信頼できる業者は、一方的な提案をするのではなく、複数の選択肢を示したうえで丁寧に説明してくれます。
例えば次のような提案があると安心です。
こうした柔軟な対応力がある業者なら、後悔のない修理が期待できます。
工事が終わってからも、トラブルが再発する可能性はゼロではありません。そのため、施工後のアフターフォロー体制が充実しているかも重要なチェックポイントです。
具体的には以下の点を確認しましょう。
施工が終わった後も責任を持って対応してくれるかどうかは、業者の誠実さをはかるバロメーターでもあります。

「自分で補修してみたけど、かえってひどくなった…」というケースでは、通常よりも修理費用が高額になる傾向があります。というのも、誤った処置が原因で被害が拡大している場合、本来不要だった補修まで必要になってしまうためです。
以下は修理費用のおおよその目安です。
| 修理内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 簡易な応急処置 | 5万円〜15万円 |
| 部分的な屋根張り替え | 20万円〜50万円 |
| 下地まで傷んでいる場合の大規模修繕 | 70万円〜150万円以上 |
費用は、被害の規模や使用する材料、屋根の構造などによって大きく異なります。だからこそ、早めの対応が費用を抑えるカギとなります。
雨漏り修理の費用は、状況によっては火災保険でカバーできる場合もあります。
特に、以下のような自然災害が原因の場合は、申請対象となる可能性があります。
ただし、注意すべき点もあります。
保険の適用を希望する場合は、まずは専門業者に被害状況の調査と見積もり書作成を依頼し、その資料をもとに保険会社へ相談するのがスムーズです。

雨漏りのトラブルは、起きてから対応するよりも「予防すること」がはるかに効果的で経済的です。ここでは、雨漏りを防ぐために日頃からできることを紹介します。
建物は年数が経つほど、目に見えない部分に劣化が進行していきます。そのため、定期的な点検が早期発見と予防のカギになります。
目安としては次の通りです。
信頼できる業者であれば、無料で点検を実施してくれるケースも多く、状況に応じたアドバイスも受けられます。
過去にどんな修理や点検をしたのか、その記録を写真・書類付きで保存しておくことはとても大切です。特に次のような情報は、将来的なトラブルの際に役立ちます。
これらを保管しておくことで、業者に見せるだけで状況の説明がスムーズになり、余計な調査費用を抑えることができるケースもあります。
DIYでの雨漏り修理は、一見コストが抑えられるように見えますが、知識・技術・経験がなければ逆効果になりかねません。
応急処置以上の作業は専門業者に依頼し、早期発見・早期修理を徹底することが住まいを長持ちさせるポイントです。
「DIY修理後にかえって雨漏りが悪化してしまった…」と感じたら、迷わず専門業者へ相談を。
『雨漏り修理の達人』では、地域ごとの信頼できる雨漏り修理業者を多数掲載中です。現地調査・点検の依頼から、修理の相談まで、お気軽にご活用ください。
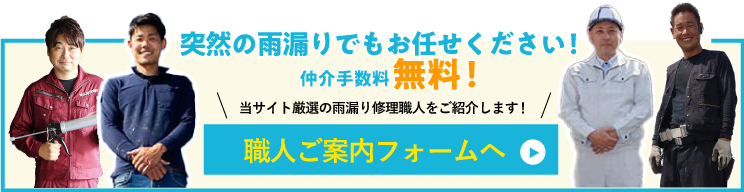
「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。
 雨漏りでよく検索されている
雨漏りでよく検索されている よく読まれている記事
よく読まれている記事お気軽にご質問ください
LINEでかんたん
問い合わせ&職人案内