ピッタリの雨漏り修理の達人は見つかりましたか?
「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。
都道府県から職人を探す
KNOWLEDGE
Tags:雨漏りの被害 | 雨漏りによる二次被害

雨漏りとシロアリの関係は、建物にとって深刻なリスクをもたらす関係と言えます。
なぜなら、雨漏りが発生すると建物内の湿度が上昇し、シロアリが繁殖しやすい環境が整ってしまうからです。
そこで今回は、雨漏りとシロアリの関係性や原因、さらに効果的な予防方法について解説します。また、定期的な点検や換気、シロアリ駆除の重要性、優良業者の選び方についてもお伝えします。
建物の安全を守るために、雨漏りとシロアリの関係を理解し、適切な予防策を講じましょう。
このページのコンテンツ一覧

雨漏りとシロアリは、どちらも建物の健全性に直接的な影響を及ぼす要素のひとつです。
はじめに、雨漏りとシロアリの建物に対する影響から見ていきましょう。
雨漏りは、屋根や外壁の劣化、雨といの詰まり、防水の不備などによって発生します。雨漏りが発生すると、雨水が建物内部に浸入し、壁や天井に水漏れやシミを引き起こします。
これによって、壁や天井の塗装や仕上げ材が傷んだり、カビや腐敗の原因になったりする可能性があります。
また、長期間にわたって雨漏りが放置されると、建物の構造材が腐食したり、家具や家電製品などの損害も発生したりする可能性が考えられます。
シロアリは、木材を主な食物として生活し、建物の構造材に被害を与える存在です。
シロアリは地下や土中を通り抜けることができるため、建物の基礎や木材に侵入し、シロアリが木材を食べることによって、建物の強度が低下する恐れがあります。
シロアリの被害は目に見えにくく、発見が遅れることがあるため、定期的な点検や被害に遭った際には早期の対策が重要になります。
雨漏りとシロアリの関係性は、シロアリによる木材の食害が雨漏りの原因となる可能性があるということです。シロアリが建物の構造材を食べることで、建物が弱体化し、雨水が浸入しやすくなるケースが考えられます。
また、雨漏りが発生した場合には、建物内部や床下などの湿度や水分が増え、シロアリの活動を促進することもあります。
このように、雨漏りとシロアリは相互に関連性が高く、建物の安全性や耐久性に悪影響を及ぼす可能性があるため、しっかりと予防することが必要不可欠と言えます。
ここでは、日本に生息する代表的なシロアリの種類について解説します。
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
ヤマトシロアリは、日本全国で広く分布しているシロアリです。
主に森林地帯や田園地帯に生息し、木材を食べて生活します。
後述するイエシロアリに比べると、やや小型で巣の形状も異なります。
建物の周辺や樹木に巣を作り、建物の木部に被害を与えることがあります。
イエシロアリは、日本国内で最も一般的なシロアリの種類です。
暖地や都市部などでよく見られ、大きな巣を作り、木材を主食として生活します。
建物の基礎や構造材を攻撃するため、建物に深刻な被害をもたらすことがあります。
アメリカカンザイシロアリは、外来種のシロアリで、日本国内でも見られることがあります。
主に温暖な地域で活動し、木材を食べて生息します。
ほかのシロアリと巣の形状や生態が異なり、特に湿度の高い環境を好みます。
ヤマトシロアリ、イエシロアリと同様に、建物の木部に被害を与える恐れがあります。
シロアリが繁殖してしまうと、建物被害がより顕著になる恐れがあります。
そこでここでは、シロアリが繁殖しやすい環境について見ていきましょう。
シロアリが繁殖しやすい環境は、以下の5つです。
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
シロアリには、湿度の高い環境を好む習慣があります。
床下空間は、地下水や排水の影響を受けやすく、湿気がこもりやすい場所と言えます。
このような湿度が高い床下では、シロアリが巣を作り、生息しやすくなります。
特に、通気性の悪い床下空間や地盤が湿潤な地域では、シロアリの被害が顕著になる場合があります。
シロアリは木材を主食としているため、木造の建築物はシロアリにとって魅力的な巣作りの場所となります。
特に、建物の主要構造や内部の木材部分が、シロアリ被害を受けやすいと言えます。
また、古い木材や未処理の木材は、シロアリの好む食料源です。
建物周辺に放置された木材や枯れ木、伐採された木の切り株などがあると、シロアリがそれらに巣を作ります。
特に、木材が直接接触している状態や地面に埋まっている場合、シロアリは容易に侵入し、被害を引き起こす可能性が高まります。
近隣の建物や庭などでシロアリの発生が確認された場合、周辺の建物もシロアリの侵入や被害を受けるリスクが高まります。
シロアリは地下や地中を通って移動するため、近くに巣があると侵入しやすくなります。
このように、建物の周辺環境にも注意することが大切です。
シロアリは、川や森林などの自然環境で生息し、そこから建物に侵入することがあります。
川や湿地帯の近くに建物がある場合、シロアリは湿度の高い環境や豊富な食料源を求めて侵入しやすくなります。
同様に、建物が森や林の周辺に位置している場合も、シロアリの被害を受けるリスクが高くなります。
森林や周辺の植生はシロアリの生息地となり、彼らの巣作りや繁殖を助長する要素となってしまいます。
建物に雨漏りが発生した場合には、シロアリ被害のリスクが高まってしまいます。
雨漏りで発生したシロアリの侵入経路は、以下の4つです。
シロアリの侵入対策も合わせて解説していきます。
雨漏りが発生し、基礎の立ち上がり部に浸水が起きると、シロアリは湿った環境を好むため、この部分を通じて建物内に侵入します。
シロアリは土中や地下を移動する能力があり、湿度の高い環境を求めて進路を変えながら進んでいきます。
雨漏りによって基礎の立ち上がり部が損傷している場合は、まずは雨漏りの原因を特定してから修理にうつります。
亀裂やダメージのある部分には防水シーリング材を使用して補修し、基礎部分の防水性を高めましょう。
また、基礎の周囲には防水シートや防水塗料を施し、湿気の浸入を防止します。
建物の基礎部分に防湿コンクリートが使用されている場合、基礎と防湿コンクリートのつなぎ目や布基礎部分がシロアリの侵入経路となります。
シロアリは細い隙間や割れ目を通って侵入し、木材を求めて進みます。
防湿コンクリートと基礎のつなぎ目や布基礎部分には、防水テープやシーリング材を使用して隙間をしっかりと閉じます。
特に、シロアリが侵入しやすい細い隙間や割れ目は注意が必要です。
防水テープやシーリング材を適切に使用し、水や湿気の浸入を防ぎます。
配管や電気配線などの貫通部分や、ベタ基礎のコンクリートの打ち継ぎ部分は、シロアリの侵入経路となります。
シロアリは細い隙間や穴を見つけて侵入し、建物内部に進入して被害を引き起こす可能性があります。
配管やコンクリートの打ち継ぎ部分には、シリコンシーリング材やポリウレタンシーリング材を使用して隙間を埋めます。
配管貫通部分には、適切なシーリング素材や防水テープを使用してシロアリの侵入を防止します。
また、コンクリートの打ち継ぎ部分もシーリング材で密封し、シロアリの侵入経路を遮断します。
基礎の断熱材や化粧モルタルの内側にシロアリが侵入することもあります。
特に、基礎断熱材の下に湿気がこもりやすい場合や、化粧モルタルの下に隙間や割れ目がある場合にシロアリが進入し、建物内部に侵入します。
基礎断熱材や化粧モルタルの内側にシロアリが侵入するのを防ぐためには、防虫ネットや防虫シートを使用して隙間や穴を覆います。
これにより、シロアリの進入を防ぎます。
また、基礎断熱材や化粧モルタルの施工には専門業者の知識と技術が必要ですので、適切な施工を行いましょう。
シロアリの被害は、早期発見と適切な対策を講じることが欠かせません。
このように素早く行動に移すためには、シロアリの被害が考えられる状況を頭に入れておく必要があります。
シロアリの被害が考えられる状況は、以下の4つです。
それでは、順に見ていきましょう。
シロアリは、エサを求めて地中を移動します。
そのため、建物周辺や床下などで蟻道(シロアリの通り道)が発生することがあります。
蟻道は土や木材の表面に見られる細いトンネル状の痕跡で、シロアリが通行するための経路となります。
蟻道が発見された場合は、シロアリの活動が近くにある可能性が高く、早急な対策が必要です。
シロアリは木材を食べる際に音を発します。
建物内にシロアリの巣が形成され活動が活発になると、建物内に乾いた音やかじる音が響きわたることがあります。
木材が食害されている場合や、シロアリの働きが進行している場合は、このような音を耳にするかもしれません。
シロアリは、繁殖のために羽アリを送り出します。
羽アリは成熟したシロアリのメスとオスであり、新たな巣を形成するために飛び立ちます。
建物内で羽アリが大量に発生する場合は、シロアリの巣が近くに存在し、被害が進行している可能性があります。
シロアリは湿度の高い環境を好むため、床下にある排水管からの水漏れがシロアリの被害を引き起こすことがあります。
水漏れによって床下が湿った状態になると、シロアリが集まり、木材を食害する可能性が高まります。
このような場合、水道代の急激な増加や床下の湿気の増加に留意する必要があると言えます。

シロアリの被害に遭ってしまうと、建物にはどのような被害が出るのでしょうか。
ここでは、シロアリによる建物被害について見ていきましょう。
シロアリによる主な建物被害は、以下の3つです。
それでは、ひとつずつ解説します。
シロアリは木材を主なエサとしているため、建物の主要な構造部材である柱や床などを食害します。
長期間にわたるシロアリの活動により、建物の木部が腐食し、建物全体の強度も低下します。
柱や床の腐食が進行すればするほど、シロアリ被害の修理範囲が広がってしまうため、最悪の場合建て替えが必要になるケースもあります。
シロアリによる木材の食害により、建物の耐震性が低下します。
柱や梁などの構造材料が弱くなるため、地震や風などの外部の力に対して建物が十分な強度を持てなくなります。
これにより、地震や自然災害に対する建物の安全性が脅かされます。
シロアリによって建物の柱や床が食害されると、建物の支持能力が低下し、傾斜や沈下が生じる可能性があります。
シロアリによって柱や床が弱くなることで、建物が不均衡な力のかかり方をするため、建物全体の傾斜やゆがみを生じることがあります。
建物の傾斜を直すには、ジャッキアップなど大掛かりな修理になるため、シロアリ被害の早期発見や適切な対策を講じることが欠かせないと言えます。
メンテナンスサイクルの目安としては、一般的な木造で新築から10年、その後は5年ごとの施工が推奨されています。
しかし、シロアリ駆除のメンテナンスサイクルは、建物の構造や立地状況などによっても大きく異なるため、一般的には年に1回定期点検を実施するとよいでしょう。
ここでは、シロアリ駆除のメンテナンスについて、以下3つのポイントを解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
シロアリ駆除のメンテナンスは、定期的な点検を通じて早期発見と予防対策を講じることが重要です。
年に1回の定期点検では、専門家が建物の状態やシロアリの活動状況を評価し、シロアリの被害や侵入経路の確認を行います。
また、点検時には予防措置や駆除の必要性を判断し、必要な対策を講じましょう。
毎年定期的に点検を実施していても、環境や建物の状況に変化が生じることがあります。
例えば、周辺地域でシロアリの発生が報告されたり、建物周辺に新たな樹木が増えたりすることも十分に考えられます。
こうした環境の変化や異常は、シロアリの侵入や被害のリスクを増加させる可能性があるため、定期点検以外のタイミングでも注意が必要です。
シロアリ駆除のメンテナンスにおいては、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
建物の状態や地域のシロアリの特性に基づいて、適切なメンテナンスサイクルや予防対策が提案されます。
専門家のアドバイスに従い、適切なタイミングでの点検や駆除を行うことで、シロアリ被害のリスクを最小限に抑えられます。
シロアリ駆除にかかる費用の相場は、依頼する業者や建物のある地域によって大きく異なります。
一般的に、シロアリ被害が確認されていない状況で、予防としてのシロアリ駆除にかかる費用の相場は、以下のとおりです。
| 業者の種類 | 費用相場(㎡) |
|---|---|
| 大手の業者 | 2,000~3,000円 |
| 地域の業者 | 1,500~3,000円 |
予防としてのシロアリ駆除の施工は、床下や建物まわりを中心に実施されます。
なお、床下の施工は施工状況を自身で確認することが難しいため、あらかじめ施工業者に施工内容の撮影などを依頼しておくといいでしょう。
雨漏りにはシロアリ被害を助長する役割があるため、適切な方法で予防することが大切です。
雨漏りによるシロアリ被害の予防方法は、以下の4つです。
それでは、個々に見ていきましょう。
雨漏りや建物の劣化はシロアリの被害を引き起こす可能性があります。
定期的な建物点検をすることで、屋根や床下、建物の傾きなどの問題を早期に発見し、被害の範囲を最小限に食い止めることができます。
なお、建物点検は、各部位の専門業者に依頼するようにしましょう。
湿度の高い環境は、シロアリの繁殖を促進します。
定期的な換気により、建物内の湿度を適切なレベルに保つことが重要です。
特に床下や屋根裏などの密閉された空間では、換気口や通気孔の確保が必要です。
湿度を低下させることにより、シロアリの繁殖や被害を抑えることができます。
シロアリは木材をエサとして利用するため、建物周辺や床下に放置された木材はシロアリの被害を助長する原因となります。
そのため、建物まわりや床下に木材を置くことはできるだけ避けましょう。
建物まわりにどうしても木材を置かざるを得ない場合には、建物から離して木材を置くことでシロアリの侵入を防ぐ効果が期待できます。
定期的なシロアリ駆除は、予防と早期発見のために重要です。
専門家によって定期的に駆除することで、シロアリの侵入や被害を抑えることができます。
駆除の方法は、建物やシロアリの活動状況に応じて適切に選択されなければなりません。
シロアリ駆除は専門知識と経験が必要なため、かならず専門業者に依頼するようにしましょう。
雨漏り修理に保険が適用になれば、自己負担額を軽減することができます。
ここでは、雨漏り修理に保険が適用されるケースについて解説します。
雨漏り修理に適用可能な保険は、以下の2つです。
それぞれ、くわしく解説していきます。
火災保険は、建物や家財などを火災による被害から保護するための保険です。
ただし、一部の火災保険には雨漏りによる被害も含まれる場合があります。
具体的な適用条件や補償範囲は、保険会社や契約内容によって異なります。
契約書の内容を確認し、それでもわからない時には保険会社に問い合わせてみるのがおすすめです。
特に、台風やゲリラ豪雨などによる雨漏りの際には、火災保険が適用されるケースが多いので、頭に入れておきましょう。
瑕疵保険は、新築やリフォームなどの建築工事において、工事不良や設計ミスによって生じた欠陥や不具合に対する保険です。
雨漏りは建築の欠陥や施工ミスによって起こる場合があります。
建築工事をした業者が瑕疵保険に加入している場合、雨漏り修理にかかる費用を保険で補償してもらうことができます。
ただし、瑕疵保険の適用条件や補償範囲も保険会社や契約内容によって異なります。
火災保険同様に契約書の内容を確認し、それでもわからない時には保険会社に問い合わせてみましょう。
業者に雨漏り修理を依頼するにあたって心配なことは、悪徳業者の存在です。
ここでは、悪徳業者の被害に遭わないために、雨漏り修理の優良業者を見つけるポイントについて解説します。
雨漏り修理の優良業者を見つけるポイントは、以下の7つです。
それぞれくわしく解説していきます。
雨漏り修理の優良業者を見つけるためには、あらかじめ屋根修理の費用相場を把握しておくことが大切です。
屋根修理の費用相場が頭に入っていれば、悪徳業者に法外な修理費用を請求される心配もありません。
雨漏り修理とそれに関連する屋根工事の費用相場は、以下のとおりです。
| 屋根修理の内容 | 修理費用の相場 |
|---|---|
| 雨漏り修理 | 5〜50万円 |
| 屋根材の部分交換 | 1〜5万円 |
| 板金部の部分交換 | 3~10万円 |
| 漆喰の補修・充填 | 3〜10万円 |
| 屋根塗装 | 50〜100万円 |
| 屋根の葺き替え | 100〜300万円 |
| 屋根のカバー工法(重ね葺き) | 80〜150万円 |
雨漏り修理の修理の費用相場を事前に把握しておけば、キャンペーンや特別値引きといった価格面の悪徳業者による被害を予防できます。
なお、これらの価格は、屋根の面積や形状、さらには雨漏りの被害状況によっても異なるため、その点には注意しましょう。
インターネットや口コミサイトなどを活用して、ほかの顧客の評判や口コミを確認しておくことも重要です。
実際にその業者を利用した人々の意見や評価を参考にすることで、業者の信頼性や技術力を把握することができます。
このような中から、多くの好評価や良い口コミを獲得している業者を選びましょう。
雨漏り修理は、専門知識やこれまでの経験がポイントになる作業です。
業者のWEBサイトやパンフレットなどをチェックし、業者がどれだけの経験を持ち、専門知識を持っているかを確認しましょう。
また、業者が所属する組合や認定資格も判断基準のひとつになります。
信頼できる業者は、経験豊富で専門知識を持ったスタッフが多く在籍している傾向があります。
複数の業者から見積もりを依頼し、価格やサービス内容、保証期間などを比較しましょう。
安価な見積もりだけでなく、修理の品質や保証内容も重要です。
契約書や細かい契約条件をしっかりと確認し、トラブルを回避するためにも、明確な契約を結ぶことが大切です。
雨漏り修理後に再発した場合や、修理後に新たな問題が発生した場合に、適切な対応とサポートが受けられるかどうかは重要です。
優良な雨漏り修理業者は、一定の保証期間を提供することがあります。
保証期間内であれば、修理後に雨漏りが再発した場合に追加費用を支払うことなく、再修理してもらえるでしょう。
そのため、保証の内容や期間をよく確認し、修理作業の品質や耐久性に自信を持っている業者を選ぶことが重要になります。
また、雨漏り修理を依頼する上で、アフターサービスも重要な要素です。
修理後に問題や疑問が生じた場合、適切なサポートやアドバイスを受けることができる業者を選ぶようにしましょう。
迅速かつ丁寧な対応をしてくれる業者は、顧客満足度が高い傾向にあります。
信頼できる雨漏り修理業者は、修理作業の品質に自信を持ち、保証期間やアフターサービスを提供することが一般的です。
これらの要素を確認することで、修理後も安心して建物を利用できるでしょう。
優良な業者は、見積もりや提案を明確かつ詳細に提示します。
見積もりには作業内容や使用する材料、費用の詳細な内訳などが含まれているべきです。
また、業者が提案する修理方法や必要な工程なども明確に説明されているかを確認しましょう。
明確な見積もりと提案は、業者の信頼性と専門知識の証拠となります。
業者とのコミュニケーションはスムーズかつ明確であることが重要です。
業者が丁寧かつわかりやすく説明してくれるかどうかを確認しましょう。
また、コミュニケーションの手段やレスポンスの速さも重要なポイントです。
信頼できる業者ほど、顧客とのコミュニケーションを大切にし、問題解決や疑問への対応を迅速に行います。
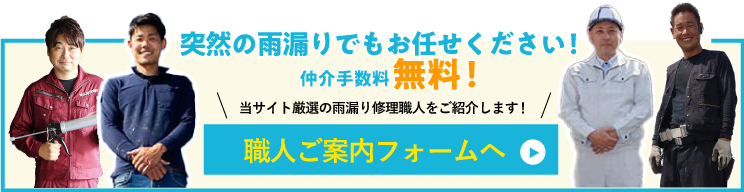
今回は、雨漏りとシロアリの関係性や原因、効果的な予防方法などについて解説しました。
雨漏りとシロアリは、どちらも建物の健全性に直接的な影響を及ぼす要素のひとつです。
雨漏りを放置してしまうと多くのシロアリが建物内に侵入し、徐々に建物に被害を与えるため、定期的な点検や適切な対策を講じる必要があります。
また、多くの場合雨漏りの原因となる屋根の定期点検は、専門知識や経験豊富な屋根修理の専門業者に依頼しましょう。
雨漏り修理の専門業者検索サイト「雨漏り修理の達人」では、雨漏り修理の優良業者を簡単に検索することができます。
職人の写真や会社情報なども確認できるので、信頼できる業者がきっと見つかるはずです。
「雨漏り修理の達人」で雨漏り修理のパートナーを見つけて、雨漏りやシロアリを予防しましょう。
「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。
 雨漏りでよく検索されている
雨漏りでよく検索されている よく読まれている記事
よく読まれている記事お気軽にご質問ください
LINEでかんたん
問い合わせ&職人案内